発達障害の子が読書を苦手とする理由5つと読書をさせるポイント4選
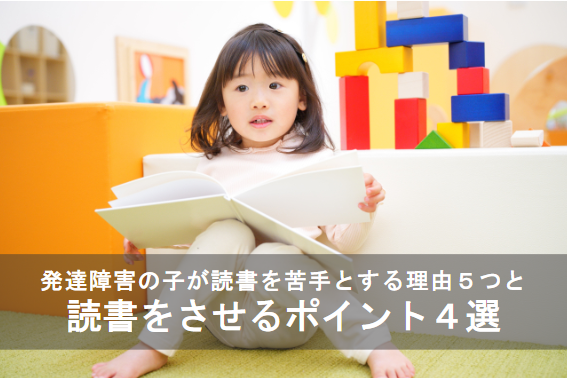

株式会社フロンティアコンサルティング 代表取締役
上岡 正明 (かみおか まさあき)
大学院にてMBA(情報工学博士前期課程)取得。専門分野は社会心理、小児心理。多摩大学、成蹊大学、帝塚山大学で客員講師等を歴任。子どもの脳の発育と行動心理に基づく研究セミナーは常に人気を博している。著者に『死ぬほど読めて忘れない高速読書』(アスコム)、『脳科学者が教える コスパ最強! 勉強法』(ぶんか社)、などベストセラー多数。中国や台湾、韓国でも翻訳され累計85万部となっている。 Twitterフォロアー5万人、YouTubeチャンネル登録者23万人を超える教育系ユーチューバーでもある。
> 監修者の詳細はこちらこの記事では発達障害のお子さんに読書をさせる方法などについてお伝えしていきます。
「本を読む習慣が全くない」「読ませようとしてもうまくいかない」「小学生になってからの国語の授業が心配」という方は少なくないと思います。
そこでこの記事では、発達障害のお子さんが読書を苦手としやすい理由や、読書をさせるための方法やポイントなどに関して解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
発達障害の方が読書を苦手としやすい5つの理由
まずは発達障害のお子さんが読書を苦手としやすい理由を4つ紹介します。
1:読書にはさまざまなプロセスがあるため
読書には、文字の形の判別→文字を捉える→文字を脳内で音に変換する→単語として捉える→単語の意味を理解する→単語をつなぎ合わせて文章として理解する→文章をつなぎ合わせて文脈を理解する、といったさまざまなプロセスがあります。
発達障害の方は複数のプロセスを同時・短時間にこなすことを苦手とする傾向にあります。
そのため親などが「読書をしないのは興味がないだけ」と決めつけず、「どうすれば読書という行為を習得できるか」も意識してサポートすることが大事です。
2:集中力が低いため
発達障害のお子さんは集中力が低い傾向にあるため読書も苦手としやすいです。
そのため静かな環境を整えるなどの方法が考えられるものの、物音などがなくても「自分の中に浮かんでくる考え」の影響で気が散って、集中できなくなるケースも少なくありません。
3:他にも楽しいことがあるため
テレビ、ゲーム、YouTubeなど他に楽しいことがあると、読書に興味が向かなくなってもおかしくありません。これは発達障害であってもなくても、大人でも子どもでも同じです。
特に読書はテレビやYouTube動画などと異なり、「勝手に入ってきてくれる情報」がほぼないため労力が大きいですし、「自分で何もしなくても楽しくなれる要素」が少ないです。そういった意味でもハードルが高いと言えます。
4:興味があるものとないものの差が激しいため
発達障害のお子さんは興味のあるものとないものの差が激しく、モチベーションが大きく変わる傾向にあります。読書に関心を持てなければ、いくら親が誘導してもなかなか読まない場合が多いです。
逆に、読書にのめり込むと何時間でも読みふける可能性もありますから、お子さんが疲弊しないようにケアしてあげることも大事です。
5:そもそも子どもにとって読書は難しいため(無理に読ませるのはNG)
発達障害であってもなくても、そもそも子どもにとって読書は難易度の高い行為です。保育園で読み聞かせを受けたり、学校の授業で国語の教科書を読んだりすることはできても、小説などを自分でじっくり読むことはなかなかできないという子も少なくありません。
その上で発達障害のお子さんの場合はここまで紹介してきたような特有の「難しさ」もありますので、無理に読ませるのはNGです。
また、お子さんの興味・関心に合う本を用意したり、読みたそうな様子を見せているときに本をすすめたりするなどの配慮をすることも大事です。
発達障害のお子さんに読書をさせるための方法・ポイント4選
それでは発達障害のお子さんに読書をさせるための方法やポイントをいくつか挙げていきます。先に紹介した読書を苦手にしやすい理由を踏まえてお読みください。
1:小説だけでなく漫画、絵本、図鑑、児童向け雑誌、ゲームの攻略本など何でも認める
まずは「活字に触れること」そのものに慣れさせることが大事ですから、小説だけでなく絵本、図鑑、児童向け雑誌など何でも認めましょう。親としては内心抵抗があるかもしれませんが、ゲームの攻略本などもおすすめです。
特に発達障害のお子さんは「嫌なこと」に対するモチベーションが極端に低くなる傾向にありますから、本人が楽しめる本を読ませることが大事です。逆に簡単な小説であっても「これを読みなさい」と強制されると読みたくなくなる可能性が高いです。
2:本をお子さんの目につくところに置く
本をキレイに本棚に並べていても、お子さんの目につかなければ手に取って読むことはしない可能性が高いです。特にゲーム、テレビ、YouTubeなど本以外の娯楽がある場合は、あえて本を読もうとはしない場合が多いです。
そのためあえて本棚から出して、居間の床、廊下、トイレの中などに散らばらせておくことをおすすめします。発達障害のお子さんは「興味を持ったらすぐ行動」という傾向にあるため本が視界に入れば手を取るかもしれません。
ただ、トイレを忘れて読みふける、寒い廊下で読み続けるなどの恐れがある場合は、居間の床など安全な場所だけに置きましょう。
3:親が本を読んでいる姿を見せる
親が本を読んでいると真似したくなるものです。また親も読書をしないと「親は読書をしないのに、なぜ自分が……」と感じ、読書をしなくなるかもしれません。
発達障害のお子さんは「親はしないけれど、自分には必要だからする」などの割り切りを苦手とする傾向にあります。
4:親が絵本の読み聞かせをする
親が絵本の読み聞かせをすることもおすすめです。特にお子さんが小さいうちは「ストーリー」というもの自体に慣れていない可能性もありますが、シンプルな内容の絵本に触れることで慣れていくものです。
特に発達障害のお子さんに対して絵本の読み聞かせをする場合のポイントをいくつか挙げます。
途中でも自由に喋らせる
発達障害のお子さんは読み聞かせの途中であっても感じたことがあれば口に出したくなる傾向にあります。それを否定せずどんどん聞いてあげることが大事です。
また、例えば「カッコイイ!」と言ったら「桃太郎はカッコイイよね」と共感を示したり、「かわいそう……」と言ったら「どうしてかわいそうと思ったのかな?」と聞いてさらに掘り下げたりするのもいいでしょう。
ただしお子さんが読み聞かせに集中しているときは、「桃太郎は今、どう思っているかな?」などと脱線させず、そのまま読み進めることをおすすめします。
お子さんの感想を否定しない
例えば絵本の内容を明確に間違って捉えているような感想が出ても、否定するべきではありません。「読み聞かせから何かを感じ取った」ということに大きな意味がありますし、否定すると読み聞かせがお子さんにとってつまらないものになる可能性が高いです。
さらに「その絵本大きいね」「お母さんの声、面白い」など絵本の内容に全く関係のない感想であっても、反応すること自体が素晴らしいです。「大きいねえ」と同意したり、あえてコミカルな声を出したりしてさらに反応を引き出すといいでしょう。
じっと座って聞いている必要はありません
発達障害のお子さんはじっと座っていることが苦手な傾向にあり、読み聞かせ中も歩き回ったり寝転がったりするかもしれません。
ただ、学校の授業ではありませんからそれでも構わないはずです。むしろ親もお子さんと一緒に身体を動かしながら読み聞かせをすることも検討しましょう。
まとめ
発達障害のお子さんは興味のある・なしの差が激しく、それが行動にも表れる傾向にありますから、できるだけ「読書=楽しいもの」という状況にしてあげることが大事です。
そのためにも、まずは漫画やゲームの攻略本など、親としては少しためらいそうな本でも「読むなら良し」と考えて受け入れてみてはいかがでしょうか。
