発達障害の子がニュースを観るべき理由3つ
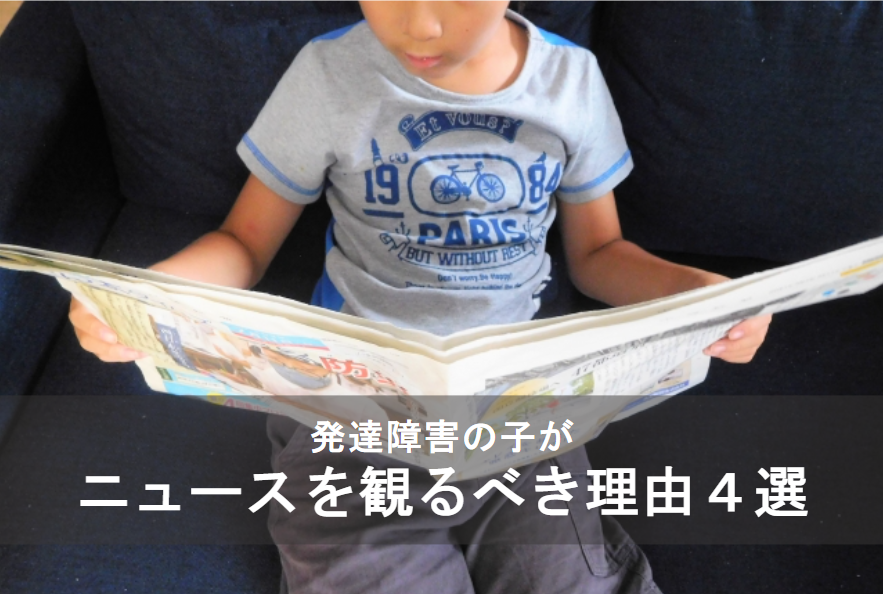

株式会社フロンティアコンサルティング 代表取締役
上岡 正明 (かみおか まさあき)
大学院にてMBA(情報工学博士前期課程)取得。専門分野は社会心理、小児心理。多摩大学、成蹊大学、帝塚山大学で客員講師等を歴任。子どもの脳の発育と行動心理に基づく研究セミナーは常に人気を博している。著者に『死ぬほど読めて忘れない高速読書』(アスコム)、『脳科学者が教える コスパ最強! 勉強法』(ぶんか社)、などベストセラー多数。中国や台湾、韓国でも翻訳され累計85万部となっている。 Twitterフォロアー5万人、YouTubeチャンネル登録者23万人を超える教育系ユーチューバーでもある。
> 監修者の詳細はこちらこの記事では発達障害のお子さんがニュース番組を観るべき理由などについて解説していきます。
「社会のことを知るためにもニュース番組を見せるべきだろうか」「見せるとしてどのようなことに配慮するといいだろうか」などと悩んでいる方は少なくないと思います。
そこで本記事では、発達障害のお子さんにテレビのニュース番組を見せるべき理由や、見せるにあたってのポイントなどに関してお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
発達障害のお子さんにテレビのニュース番組を見せるべき3つの理由
まずは発達障害のお子さんがテレビのニュース番組を見せるべき理由を3つ挙げていきます。
1:外の世界にも意識を向けるため
発達障害のお子さんは自分の世界に入りがちです。
その世界を守りつつも、外の世界に意識を向けるためには、ニュース番組などを通じて「自分が関わらない世界でも毎日何かが起きている」「世界にはさまざまな考えや価値観を持った人がいる」と自然に教えることが大事です。
2:情報を整理する能力を付けるため
発達障害のお子さんは情報を処理する能力が低い傾向にありますが、ニュース番組を観ることでその能力を鍛えることができます。討論番組などよりは情報量が少ないものの、「新聞の見出しのみ」などに比べると情報が多いためちょうどいいです。
3:テレビのニュースであれば興味のない情報も入ってくるため
インターネットを使うことでもニュースを探せますが、ネットの場合は自分の興味のある情報ばかり探してしまう傾向にあります。
それも悪いことではないものの、徐々に「自分の世界」に逆戻りしてしまい、ニュースを見る意味が薄くなるかもしれません。
そのため興味のない情報も無差別に入ってくるテレビのニュース番組がおすすめです。また、情報番組であればシリアスな情報も楽しい情報も入ってきてメリハリがあるため、お子さんが情報番組自体に興味を持っている場合はある程度長時間見せるのもいいでしょう。
発達障害お子さんにテレビのニュース番組を見せる際の5つのポイント
それでは発達障害のお子さんにテレビのニュース番組を見せるときのポイントをいくつか挙げていきます。親が的確にサポートすることにより、お子さんにとってよりニュース番組を観やすくなります。
1:親が(主観を交えず)子どもにわかりやすい言葉に変換する
例えば年金情報流出関連のニュースがあった場合は、「60歳くらいになってからお金をもらうために、みんな今のうちからお金を国に預けているんだよね」「けれどお金をもらうための情報が他のところにも流れてしまったんだ」などと子どもにもわかりやすく説明します。
年金情報流出の説明として微妙に間違っているかもしれませんが、あくまで理解しやすさを重視することをおすすめします。
また、お子さんの考えが偏らないようにしたり、お子さん自身に考えさせたりするためにも、親の主観はできるだけ混ぜない方がいいでしょう。年金情報流出関連では、例えば「○○省のせいだね」「そもそも年金のルール自体が……」などとは言わないということです。
2:デリケートなニュースについても極力解説する
ニュース番組を観ていると殺人事件、戦争、テロなどデリケートな情報も流れてきます。これらについてもお子さんにわかりやすく説明することをおすすめします。なぜならこの世界で起きている出来事であることに違いはないからです。
ただ、例えば戦争であれば「国同士がケンカをしている状態」と柔らかい表現を使ったり、逆にシリアスな言い方をしたりと、お子さんの成長や性格に合わせて伝え方を変えるといいでしょう。
3:お子さんが不安を感じていれば対処法・予防法なども教える
お子さんがニュースに対して不安を感じている場合は、対処法・予防法などを具体的に教えることをおすすめします。発達障害のお子さんはあいまいなアドバイスを理解しにくい傾向にあるため、「心配しなくても大丈夫」で済ませず、掘り下げて伝えることが大事です。
例えば誘拐事件のニュースで不安になっている場合は、「できるだけ一人で外を歩かないようにしようね」「何か怖いことがあったらとにかく大きな声を出して逃げよう」「何があっても知らない人についていってはダメだよ」などと教えます。
4:興味がある話題は深掘りして調べてみる(調べさせる)
お子さんが特定のニュース・情報に興味を持った場合は、深掘りして調べさせることをおすすめします。「興味のあることのために、情報を集めて理解を深める」という行為に慣れておくと、学校の勉強でも、社会に出てからの仕事でも大いに役立ちます。
お子さんが慣れるまでは親がインターネットで調べて情報を見せてあげたり、ニュース番組を録画したりしてあげるといいでしょう。慣れてきたらお子さん自身にやり方を教えて、自力でできるように導きます。
ちなみに追いかける情報・ニュースは社会的なものでなくても構いません。「あの俳優が他に出ているドラマは?」「あのノーベル賞受賞者をサポートしたのは誰?」「今日紹介されたあの地域のお祭りの歴史は?」などの情報・ニュースを深掘りするのもいいでしょう。
5:ニュース番組を観ていなければテレビを消す
観ていなくても音声は聞こえ続けます。そして積極的に聞くつもりがなくても情報過多になってお子さんが疲弊するかもしれません(発達障害の方の場合は特に)。なのでお子さんがテレビを観ていなければ消すことをおすすめします。
またニュースのことを抜きに考えても、「テレビを観ていないときは消す」という当たり前の習慣を身に付けたいところです。
まとめ
特に発達障害のお子さんにとってテレビのニュース番組は「単なる情報源」という以上に、「外の世界を知るためのツール」という意味合いが強いです。そのため食事など他の行動に支障をきたさない範囲で積極的に見せることをおすすめします。
お子さんが特に気にする情報があればさらに調べさせたり、親子でその情報について話し合ってみたりしても面白そうですね。
