発達障害の子からの「宿題をする理由って何?」に対する答え4選
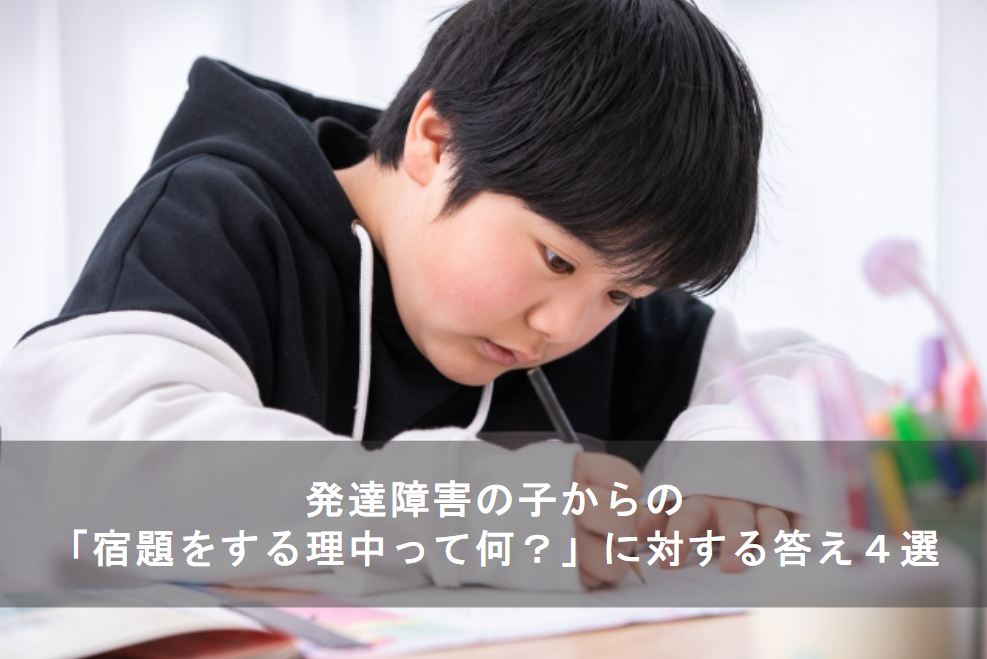

株式会社フロンティアコンサルティング 代表取締役
上岡 正明 (かみおか まさあき)
大学院にてMBA(情報工学博士前期課程)取得。専門分野は社会心理、小児心理。多摩大学、成蹊大学、帝塚山大学で客員講師等を歴任。子どもの脳の発育と行動心理に基づく研究セミナーは常に人気を博している。著者に『死ぬほど読めて忘れない高速読書』(アスコム)、『脳科学者が教える コスパ最強! 勉強法』(ぶんか社)、などベストセラー多数。中国や台湾、韓国でも翻訳され累計85万部となっている。 Twitterフォロアー5万人、YouTubeチャンネル登録者23万人を超える教育系ユーチューバーでもある。
> 監修者の詳細はこちらこの記事では発達障害のお子さんからの「どうして宿題をするの?」に対する答えなどについて解説していきます。
「宿題をする理由に関して子どもを納得させることが難しい」「親である自分としても、実は宿題に対して疑問を抱いている」という方は少なくないと思います。
そこで本記事では「宿題というものの存在意義」や、「宿題をする理由4選」などを紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
学校の宿題が役立つかわからなくてもこなす必要はある|発達障害ケア
日本の学校の宿題は、漢字ドリル、計算ドリルなど画一的で、お子さんにとって率直に言ってつまらないものが多いです。発達障害であってもなくても完全に納得して取り組んでいるお子さんは少ないことでしょう。
特に得意分野・苦手分野、興味のある・なしの差が激しい傾向にある発達障害のお子さんの場合、学校の宿題によって学力などを伸ばしていけるかどうか疑問に感じている保護者の方は少なくないと思います。
とはいえ基本的に「だからうちの子には宿題をさせないでください」「宿題の内容を変えてください」と学校側に訴えるわけにもいかないはずです。お子さんだけでなく、親も割り切って宿題をこなす必要があります。
どうしてもお子さんの負担が大きい場合は相談して宿題の内容・量を調整する
ただ、特に学習障害などで通常の宿題をこなすことが難しい場合は、学校側と相談して宿題の内容・量を調整してもらうことをおすすめします。宿題の内容・量があまりにもお子さんに見合わないとなると、宿題をする意味がなくなってしまいやすいからです。
学校側と相談するにあたっては「何とかしてください」と丸投げするのではなく、以下のようなことを伝えるのが大事です。
- うちの子にはこういった特徴があります
- だからこのように宿題の内容や量を調整していただきたいです
- 難しい部分もあると思いますがご検討をお願いします
なぜ宿題をするのと聞かれた際に伝えられる理由4選|発達障害ケア
それでは発達障害のお子さんに「なぜ宿題をするの?」と聞かれたときに理由として答えられるものをいくつか挙げていきます。この「理由」についても親として100%納得できる日は来ないかもしれませんが、ある程度割り切った上で伝えることが大事です。
1:将来の仕事に備えて|今はこれがあなたの仕事だから
「将来お仕事をするときに備えて」「今はこれがあなたの仕事だから」という答えはなかなか有効です(お子さんを過剰に子ども扱いしないという意味合いもあります)。
将来企業で働く場合はもちろんですが、フリーランスになるとしても納期・ノルマなどがほぼ確実にありますし、それを破らないためのスキルが必要です。宿題はそのスキルを身に付けるための練習とも言えます。
お子さんにはもう少しわかりやすく「将来会社に入ったら締め切りを守らないといけないから宿題はその練習だよ」「会社に入ったときのために今から練習しておくんだよ」などと伝えるといいでしょう。
2:人間は忘れる生き物だから
人間はその日に学んだことの70~80%は忘れると言われています。特に授業で一回触れただけの内容は大半を忘れると考えておくべきです。そのため「人間は忘れちゃう生き物なんだよ」「だから覚えておくために宿題をするんだよ」などと伝えるといいでしょう。
ただ、この答え方は「授業でやっている部分」と「宿題として出される内容」がズレていると説得力が下がりやすくなります。なのでお子さんの授業ノートや宿題の内容をチェックしてから、言うことをおすすめします。
3:自宅で勉強する習慣をつけるため
学校で宿題が出されない限りは、お家では机に向かわないお子さんがほとんどだと思います(発達障害であってもなくても同じことです)。
そのため「お家の中だと勉強しない子が多いから勉強の習慣を作るためだね」「中学生や高校生になるとどうしてもお家で勉強する時間が増えるから、今のうちに練習しておくんだよ」などと伝えることをおすすめします。
4:もっと勉強できるようになるため
お子さんの性格などによってはストレートに「お家でも頑張ってもっと勉強できるようになるためだよ」「先生は子どもたちにもっと勉強できるようになってほしいと思っているんだよ」などと伝えるのもいいでしょう。
ただ、この聞き方をする場合は「じゃあなんでもっと勉強できるようにならないといけないの?」「授業にはついていけているよ」などと言われた際に、さらにどのように答えるかも考えておく必要があります。
もしくはお子さんがこのような疑問を抱くと予想できる場合は、「もっと勉強できるようになるため」ではない別の答えを用意します。
ご家庭なりに「宿題をする理由」を考えていきましょう
もちろん今回紹介した「宿題をする理由例」をそのままコピーするのではなく、ご家庭なりに考えていただければと思います。お子さんに「全然感情が入っていないな」などと思われてしまえば、信用を失ってもおかしくありません。
例えば「将来自宅でも仕事ができるようにするためだよ」と今回紹介した内容を組み合わせるのもいいですし、お子さんの性格や成長度合いによっては「○○さん(お子さんの憧れの人物・キャラクター)も宿題をちゃんとやっていたらしいよ」などと言うのもいいでしょう。
お子さんがさらに成長し、その上で宿題に関して悩みを抱えている場合は、親の方から「ねえ、どうして宿題をしないといけないんだと思う?」などと問いかけて、話し合ってみるのもおすすめです。
まとめ
宿題をすること・宿題の内容や量について完全に納得しているお子さんは、発達障害であってもなくてもほぼいません。また、発達障害の方は「割り切り」が苦手な傾向にありますから「どうして宿題をするの?」と聞かれたら、親がある程度答えることが大事です。
もちろん「これが正解」というものはありませんし、家庭によっても変わってきます。ただ、いずれにせよ「考えること」をして、お子さんが最低限納得できるような答えを用意してあげましょう。
