発達障害の子に適切な声量調整をさせる5つのポイント
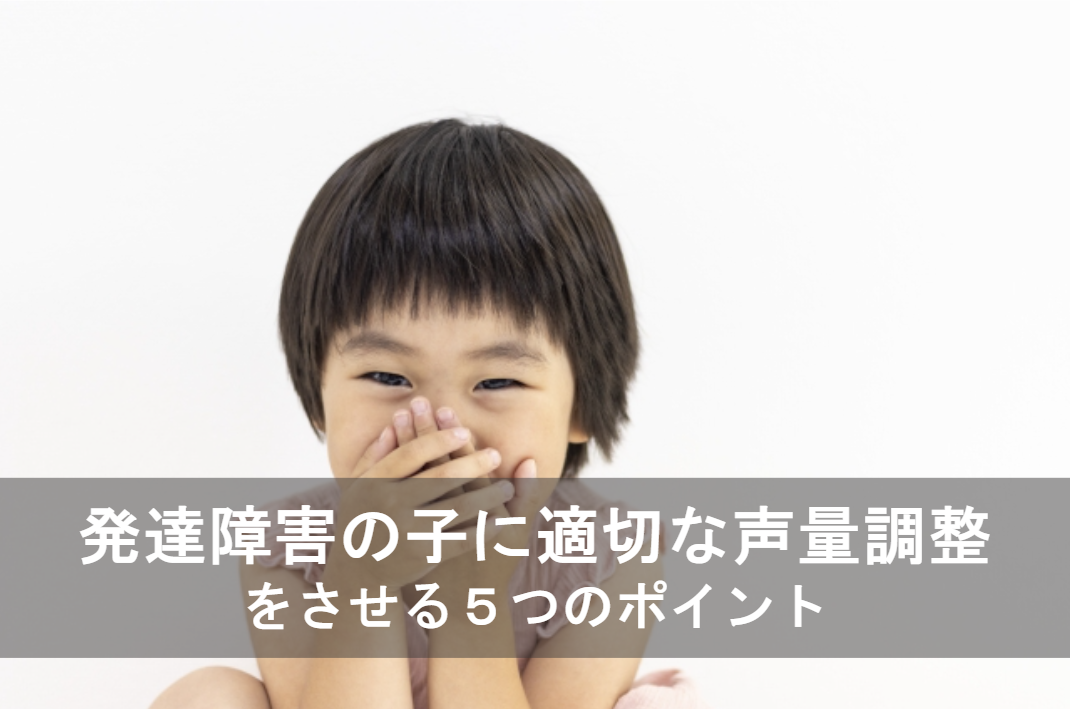

株式会社フロンティアコンサルティング 代表取締役
上岡 正明 (かみおか まさあき)
大学院にてMBA(情報工学博士前期課程)取得。専門分野は社会心理、小児心理。多摩大学、成蹊大学、帝塚山大学で客員講師等を歴任。子どもの脳の発育と行動心理に基づく研究セミナーは常に人気を博している。著者に『死ぬほど読めて忘れない高速読書』(アスコム)、『脳科学者が教える コスパ最強! 勉強法』(ぶんか社)、などベストセラー多数。中国や台湾、韓国でも翻訳され累計85万部となっている。 Twitterフォロアー5万人、YouTubeチャンネル登録者23万人を超える教育系ユーチューバーでもある。
> 監修者の詳細はこちらこの記事では発達障害のお子さんに適切な声量調整(声の大きさの調整)をさせるためのコツなどについて解説していきます。
「場違いな大きさの声を出すときがあって困っている」「どうすれば声の大きさをコントロールできるようになるのかわからない」と悩んでいる方は少なくないと思います。
そこで本記事では、発達障害のお子さんが声量調整を苦手としやすい理由や、声量調整をさせるためのポイントなどに関してお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてください。
発達障害のお子さんが声量調整を苦手としやすい3つの理由
まずは発達障害のお子さんが声量の調整を苦手としやすい理由をいくつか挙げていきます。理由を知ると「声の大きさに気を付けて!」と指示するだけではうまくいかないとわかるはずです。
1:そもそも「声量を調整する必要がある」という感覚がない
特に小さなお子さんの場合は、場面によって声の大きさを変える必要があるということ自体をわかっていない可能性があります。
大人からすると理解できない感覚かもしれませんが、「非常識だな」「信じられない」などで済ませずきちんと教えてあげることが大事です。
2:どの場面でどのような声量であればいいのかを知らない
例えば「病院ではひそひそ声に留める」「普通の会話で声を張る必要はない」など、どの場面でどのような声量であればいいのかを知らない可能性もあります。知らないのですから本人に悪気はありません。
ただ、場面ごとの適切な声量については比較的簡単に理解できるようになるはずですので、それほど心配する必要はありません。
3:声量のコントロールに慣れていない
「声量を調整する必要がある」「この場面ではこれくらいの声量であるべき」と理解していてもそれを実践できないお子さんもいます。
ただ、これについても慣れていけばできるようになりますし、(詳しくは後述しますが)「微調整する」のではなく、「数段階で大雑把に調整する」と考えればそれほど難しくはありません。
発達障害のお子さんに声量調整をさせるための5つのポイント
それでは発達障害のお子さんに適切な声量調整をさせるためのポイントをいくつか挙げていきます。
1:声量のレベルは最低3段階あればいい
声量調整と聞くと「0~100でアナログな調整をする」と感じるかもしれませんが、実際には最低3段階の調整ができればそれで十分です。その3段階とは以下の通りです。
- 2:普通の声量(普段の会話など)
- 1:ひそひそ声(病院の待合室でどうしても話すことがある場合など)
- 0:全く喋らない(病院の待合室など)
お子さんには「今は声、0だよ」「1にしようね」などと明確に指示を出すことをおすすめします(発達障害の方は曖昧な指示を理解しにくい傾向にあります)。お子さんが慣れてきたら、「3:通すための声」「4:危険を知らせるための大声」なども追加するといいでしょう。
動物で例えると理解しやすい場合も
0、1、2などの数字ではなく「アリ(0)」「ウサギ(1)」「猫(2)」「ライオン(3)」などの動物で例える方が理解しやすい場合もあります。
ただ、もちろんかえってわかりにくくなる子もいますから、お子さんの特徴に合わせて「数字(0、1、2……)」「具体的な表現(無言、ひそひそ、普通……)」「動物(アリ、ウサギ、猫……)」などを使い分けることをおすすめします。
2:声量スケールを作る
声量スケールとは先に紹介した「声量レベル」に表情のイラストや簡単な説明を入れたもののことです。例えば以下のように作ります。
- 4:危険を知らせる大声だよ(大きく口を開いて顔を赤くして喋るイラスト)
- 3:大きな声で発表するよ(大きく口を開いて喋るイラスト)
- 2:会話の声だよ(普通の表情で喋るイラスト)
- 1:ひそひそ声だよ(口にパーの手を当てて喋るイラスト)
- 0:しゃべらないでね(シーっと口に指を当てたイラスト)
外出時なども声量スケールを持ち歩き、「ここではひそひそ声だよ」などと、イラストに指を当ててお子さんに説明してあげるといいでしょう。
3:親が「これくらいの声だよ」と声を出す
親がその場で「これくらいの声だよ」と適切な大きさの声を出せば一目瞭然です。
ただし大人でも声量調整が苦手な人はいますので、「自分も声量調整に自信がない」という人は他の方法を取る方が無難かもしれません。とはいえ「今はひそひそ声だよ」くらいの指示は出せるはずです。
4:「ここではどれくらいの声量がいいかな?クイズ」で遊ぶ
普段からお子さんに「こういった場所に行ったら、これくらいの声量がいい」「こういう場面だとこれくらいの大きさで喋る」などとイメージさせるためにクイズをして遊ぶのもいいでしょう。例えば以下の通りです。
- 映画館で映画を観始めたらどれくらいの声がいいかな?→無言
- 病院の待合室でどうしても喋らないといけないときは?→ひそひそ声
- 学校の教室で作文の発表をするときは?→大きめの声
また、声量調整に限らず、発達障害のお子さんに何らかのトレーニングをさせる場面は多いと思いますが、「これはトレーニングだよ」という態度を親が見せると一気にやる気を失うかもしれません。あくまでクイズ遊びという態度で臨みましょう。
5:適切な声量に調整できたら褒める
適切な声量に調整できたりクイズに正解できたりしたら、しっかり褒めましょう。褒めることで自信が付きますし、褒めてこそ「この声量で良かったんだ」と実感できるからです。
喋っていい場面であれば「うん、その声の大きさでバッチリだよ」などと言葉で言えばいいです。そして黙っているべき場面において無言でいられた場合は、後で「○○のとき黙っていられて偉かったね」などと褒めましょう。
まとめ
大人からすると忘れがちな感覚ですが、そもそも「声量調整をする必要があると知らないかもしれない」と考えることが大事です。これはお子さんが発達障害であってもなくても同じことです。
あまり細かな調整はさせず、最低3段階ほどコントロールできれば十分ですので、まずは気軽に取り組んでみることをおすすめします。
